2017年にベストセラーにもなり、映画化もされた有名作品です。本は自分の悪性リンパ腫の初発時に持っていたのですが、なかなか読む気になれませんでした…。結果的に読んだのは2025年となり、読みながら自分の変化を実感することになりました。
病気になってから、自分は「時間」を気にする傾向が強まりました。「短時間に」「合理的に」「効率的に」という感覚が強まり、小説などの「文脈」を大事にする時間が減りました。
その「感性」の変化を、この本を読みながら感じることが強かったです。いかんせん「何が言いたいのか?」と思う瞬間が多い。昔の自分にはあまりなかった感覚が、この本を読みながらはっきりとわかりました。それだけでも、自分としては大きな収穫です。
内容としては、自分が病人と言う立場もあって思う所は人とかなり違う気がします。タイトルの意味も、捉え方は少し違ったような気がします。
大意としては「相反する二人」がお互いを認め合っている結果なんだろうと思っています。「相手の一部を取り入れたい」という想いが、結果的に「君の膵臓をたべたい」という言葉になっているのであろうと。
病気になると、勝手ですが確かにその病気で自分は死ぬと錯覚します。言い方を変えると、「その病気で死ぬまで死なない」となります。もちろんそんなことは無くて、抱えている病気以外にも事故やその他で死ぬことは当然あるんですよね…。そんな当たり前に気づかされる作品です。
本文の中に「××くんは『真実』と『日常』をくれる」とあります。これは、似たことを私も思ったことがあります。
入院していると、一番に感じるのが自分の今までの日常生活の、相対的な幸せです。ご飯を食べる、歩いて移動する、手が動く…。そんなことが、いかに幸せだったかを実感します。日常に、とても幸せと愛おしさを感じます。
病人とはいえ、特別扱いを…してほしい時と、してほしくない時が面倒ながらあります。当たり前の日常を、自然に用意してくれる人がどれほど稀有な存在かを認識させられますね。
「医者は真実だけ、家族は日常だけ」という表現がまさにぴったりで「真実を知りながら日常をやってくれている存在」は、主人公の意識とは別にとてもかけがえのないことであったんだなと思うわけです。これも、病人の視点ですが。
「生きる」ということについての言及も、私にとって印象的です。「生きる」とは、本当に他人がいないと成り立ちません。誰かを「認める」「嫌いになる」「うっとうしい」「ハグしたい」といった感情と行為は、「誰か」があって成立します。
「自分一人じゃできないし、自分がいることでさえ認識できない」という記載は、まさに「誰かがいるからこそ、自分を認識できる」ということに他なりません。
第三者の存在と、自分との関係性について。そして病気をもった自分との考え方について。いろいろ思うことがある一方で、入院中に読むと少し苦しかった様に感じます。そこに気が付いた(と言うより、勝手に察知した)自分の本能に、少し驚きました。
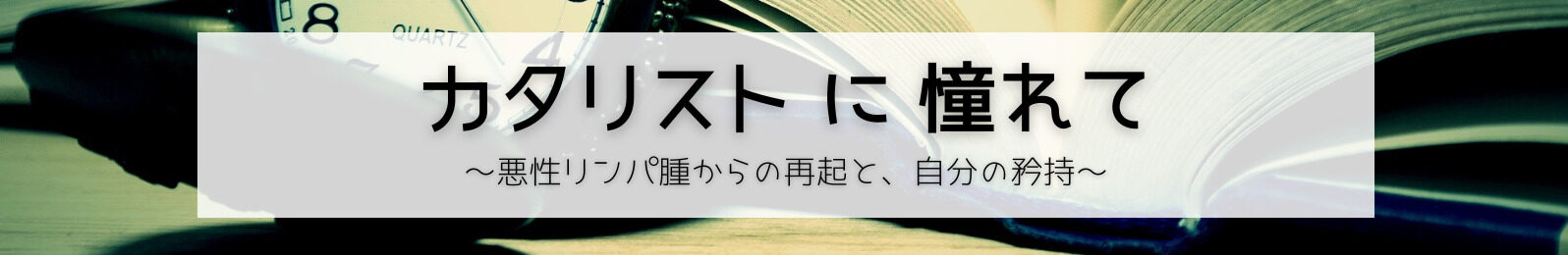

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/43ded940.c5c16099.43ded941.cac05dcd/?me_id=1213310&item_id=18457613&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9945%2F9784575519945.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)


