まとまった時間があると、最近は会計学の本をよく読みます。大学時代に専攻していて、今でも関心があることが大きいです。一方で、無機質な会計学に疑問を持って、大学時代の卒論は「行動経済学」であることは、私の性格的なモノなのかもしれません。
「数字は事実」という一般的なイメージを、私は持っていません。むしろ、その感性を培ってくれた著者との出会いがあることが大きいです。その著者の作品をいくつか読んだ中で、ある程度まとめた内容を書いていこうかと思います。
1 財務と非財務
私が会計学に関心を持ったきっかけは、客観性にありました。「数字とはウソをつかない」という価値観を、最初は持っていました。簿記のテキストなどを見ても、正解は一つで具体的な解答があるのが当然です。
しかしながら、粉飾決算等の事例を見ていくうちに、ずいぶんと恣意的に数字は捻じ曲げられるのだという印象も徐々に持ち始めました。もちろん合法的な内容もありますが、もっとも大切なのは「その数字を使ってどうしたいのか?」という感情的な内容も大きいという結論に至ったことを覚えています。
「決算書には全ての価値は載っていない」という一文は、まさに会計の弱みを表しています。製品の将来性や社員のスキル、人材の労働意欲などは会社を構築する重要な要素ですが、会計上には一切現れません。現在人事として業務をしている自分は、特にその点が気が掛かりですね。
では数字に意味がないのかと言うと、そういうわけでもないのが難しいところです。具体的な数値にしないと、改善のコントロールが出来ないからです。違和感やきっかけを探すためには、間違いなく会計の知識やセンスが問われると思います。
一方でその数値を鵜吞みにして、赤字の原因を人件費と特定することは合理的とは言えません。単純に従業員の給料カットに走ることは、目に見えない会社の財産(人材のスキルや労働意欲等)を削る最も不合理な意思決定と成り得るからです。会計数値を客観的事実として対応することは、とても危険性を孕んでいます。
有名どころをもう一つ上げるとすると、企業の「利益信仰」についてです。利益とは主に「売上 ー 費用」の計算結果として扱われますが、これを最大化することが必ずしも合理的とは言えません。利益が蓄積しても、儲かっていないかもしれないという事実を早目に認めなければいけません。
そもそも「儲け」というのは会計学上の利益の大小ではなく、実際の現金の蓄積と回転にあると私は考えています。目に見えて現金が増えることと、会計上の利益が出たということは全くのイコールではありません。日常生活においては割と納得しやすいこのイメージが、企業の決算では変わってしまいやすい事実があります。
売上に関わる重要な要素として「製品単価」が挙げられますが、この価格決定についても一般的なイメージと異なる点があります。費用を上回る価格を設定することは、計算上利益を生み出すことになります。一方でこの考え方には「顧客主体」という視点が、欠けていることが問題です。
企業が計算上必要と示した価格に対して、顧客が満足して金額を支払うかどうかを何よりも検討しなければいけません。言ってみれば価格を決めるのは「企業」ではなく「顧客」という考え方が、とても重要になります。
そもそもモノを買う時の立場として、価格を最重要基準にしているかは人によります。デザインや実用性、さらに抽象的に言うと「幸せ」や「満足感」といった要素によって購入可否が変わることが自然です。企業の設定した価格を、顧客が受け入れるかどうかは全くの別物と考えた方が良いです。
2 在庫とキャッシュフロー
在庫の概念は非常に複雑で、扱い一つで粉飾に繋がる可能性も孕んでいます。ただ、あえてシンプルに設計をすると「在庫=現金の仮の姿」と表現するのが、一番しっくりきます。
在庫とは現金が眠っている状態であり、運転資金の滞留の根幹にあるというのが現実です。家計においても、家の中に積まれた日常品のストックも在庫の様なモノと考えられます。現金が不足する多くの原因は、過剰な在庫ともいえるのではないでしょうか?
「いずれ使うものだから」と言う考えももちろんあるかもしれませんが、在庫は盗難や劣化のリスクも同時に孕んでいます。家計の食品で言うと、期限切れや品質劣化の廃棄は「現金を捨てている」と言うことと、同義であります。キャッシュフローの改善には「在庫」をいかに少なくするのかという視点が重要であり、巷で叫ばれる「固定費」の削減よりも優先されるものではないかとも考えます。
企業でも家計でも必要最低限の在庫に抑えることは、論理的にはとても理に適っています。一方でその考えはそこまで一般的…とは思えません。小ロットで少ない運転資金を高速で回す仕組みを企業でも家計でも取り入れるべきであると考えますが、その考えは機会損失に対してどうしても保守的になります。
売れるはずだった製品を売れないことで、得られないメリットを人はどうしても大きなものに見てしまいがちです。結果的に何も損はしていないのに、機会損失と言う名前がついていることからもその影響は大きいでしょう。だからこそ、企業はある程度ゆとりを持った在庫(たくさん買えば規模の経済性で安くなることも)が、どちらかと言うと自然なのかもしれません。
ただ、少なくとも仕掛け品や近時の在庫の推移から明らかな増加がみられるときには、会計学的には注意が必要です。異常が起きている兆候の代表的な事例と、私は考えます。
「利益ポテンシャル」という言葉を、ご存じでしょうか?いくつか意味があるようですが、私は「限界利益/在庫金額」と捉えています。言葉にすると「利益率が高く、回転速度が速い製品を販売するとメリットが大きい」となります。
どちらかに特化することも戦略なのかもしれませんが、この2つの軸が回る製品を開発していくことが企業の使命なのかもしれません。利益至上の価値観ではなく、キャッシュ主体の価値観であれば尚のこと強く感じます。
3 コストと費用
私の中で個人的に区別しているのが、この2つです。定義としては「費用」は売上に貢献する必要な経費(削ってはいけない)であり、一方で「コスト」は売上に貢献しない不要なモノ(削るべき)というイメージです。あくまでも、私なりの感覚ですがね。
コスト削減と言いつつも、必要な「費用」を削ることが企業にとってプラスになるわけがありません。さらに言うと家計においても削るべきではない「費用」を削減することが、人生の豊かさに悪影響を及ぼしていると考えます。
これは時間管理においても重要な視点で、24時間という限られた時間資源の中で必要な「費用」としての時間を削減してしまっていないでしょうか?代表例が「睡眠時間」ですね。必要な「費用」としてのお金や時間を削減することが、企業や個人に与える影響は甚大です。いかに不要な「コスト」を削減するのか(人によって違うことが問題を複雑化している)を常に考えなければいけません。
話を企業に戻して、もう少し具体化します。一般的に「間接費」とされる費用(固定費と混同されがち)は、利益に貢献している働きは10~20%程度と言われています。大半が無駄に使われることから「間接費」は削減すべきものとされる現実があります。
ただ、全て闇雲に削減していいモノではなく、例えば事務職を全員解雇するということは愚行の極みです。利益に貢献していない可能性もありますが、必要だから発生している(大半が固定的に)費用を一律に削減することが良いわけありません。金額の多寡や「間接費だから」という理由ではなく、売上への貢献を客観的に見つめ直す必要があるでしょう。
一方で、これを「仕事」に置き換えて考えると、間接的な仕事の大半はコストである可能性があることも重要な視点です。「どうでもいい仕事」を、日々黙々と行っている可能性はないでしょうか?特に古くからの慣習として行われていることを当然のこととせず、本当に必要なのかどうかを今一度考えてみることも大切なのかもしれません。
仕事とは顧客満足のためにあり、そのために使われる「費用」は削減してはいけません。顧客が満足して金額を支払うことで全ての負担をしているという事実があり、コストカットが結顧客満足を下げてしまっているのであれば、それは見直す必要がある(会計学上の正しさは、現実的に正しいわけではない)ことに他なりません。
長くなりましたので、続きは後半にしたいと思います。
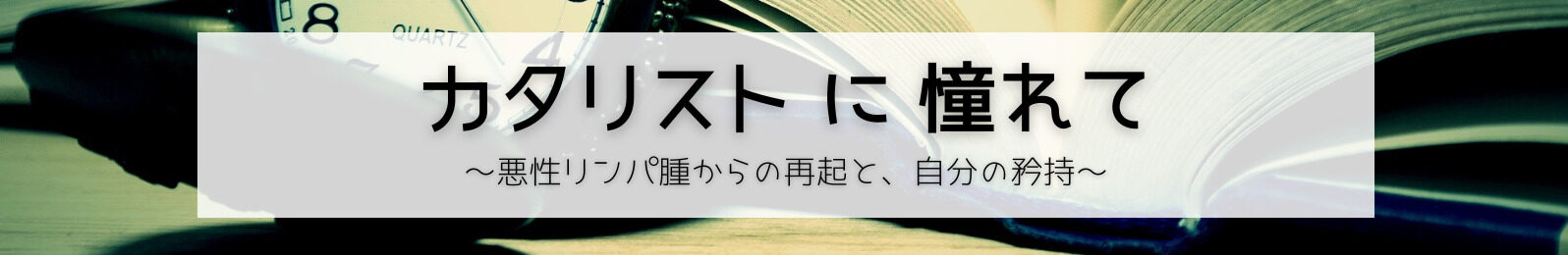

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45330b1f.368f98cd.45330b20.29ea5a4e/?me_id=1278256&item_id=13067746&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F3392%2F2000001713392.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


