前回に引き続き、絶対悲観主義の要約です。読み応えがあった分、記載の内容も出来るだけ減らしてもこの分量になっているのが困るところですね…。
本の中には、人間の思考の本質について具体例を挙げて説明している箇所がいくつかありました。その中でも、共感が強かったところを記載していきます。
人間の「悩み」を突き詰めていくと、結局この2つになると記載があったのが「健康」と「平和」です。今までこの結論になった記憶がなかったので、なかなか面白いなと思いました。
2つとも特徴として「失ってから始めて大切さに気付く」とあったのが、まず初めのインパクトです。病気をした側の人間としては「健康」については理解が速かったのですが、もう一つの「平和」についても確かに本質は同じだと思いました。
不満は少なからずあれど、衣・食・住に困っていない日本の私の状況。戦争下にある人から見れば、私の悩みなど取るに足らないことなのでしょう…。
結局はこの2つが充足している(不足に気づいていない)からこそ、次のステージの高次な悩みが生まれるのであって、この2つのうちいずれかが不足して入れれば、新たな悩みなど増えていかないんですよね。
「健康」には病気という大きなテーマだけでなく、もう一つ「老い」というテーマも含まれています。昨今は老人の「幼児化」が顕著になっており、自分都合だけで物事を考える老人が目に付くようになっているそうです。
…まぁ、私生活でもそういう人に確かに気が付くようになっています。
原因は「知性」の欠如に起因しており、これは「個別具体的な事象の背後にある本質を抽象化」が出来なくなっているとこの本では定義づけられています。知性や教養が欠如している老人が増えてきていて、自分勝手が増えている…一体この国には何が起きているのでしょうか?
「愚かな選択」とされる戦争が、なぜ歴史上繰り返されるのか?その背景には「貧すれば鈍する」ということが、往々にある様に感じます。どんなに優秀な人でも、追い詰められたり生命の危機(健康の不足)にあったりすると、この選択を取ることを歴史が証明しています。
どんな反対があっても戦争は開始され、いずれ「自分は正しい判断をした」という正当化の名の下に多くの犠牲が払われます。まさかこの本からこんなことを学ぶとは、思いもしませんでした。
★
次のテーマは「お金」と「時間」です。この話題は、他の本でもよく見る話題です。どちらが大事かと言うと「時間」の結論はよく見ますが、この本ではその考察が一味違って面白かったですね。
よくある話として「お金から得る幸福は限界効用にて逓減する」という話が、この本でも述べられています。一定の満足を得てしまえば、お金から得る幸せはそんなに増加しないというモノです。
これは物欲的には自分の実感もあって、もうそんなに欲しいモノってないんですよね。健康であれさえすれば、後は今の水準で別にいい。
あくまでお金はお金という「便利なツール」としての立ち位置での運用が、私も必要であると感じています。「価値を図る物差し」であることや、何かとの「交換」の兌換性、一定の「貯蓄性」という観点は確かに有効だと思います。
物々交換の時代には戻れませんし、お金は腐らないので(経済性的に、価値は相対的に変わりますが)。
面白かったのはココからで、人の行動を「お金」を通して見るという視点は新鮮でした。お金を掛けているモノ以上に、その人が「お金を掛けていないモノ」を観察することでその人の本質が見える…という考えは、全く持っていませんでした。
確かに人によって、お金の価値観や掛け方は全然違います。これは、私の仕事である「採用面接」にも応用出来そうだと思いました。
「時間」は誰にでも平等に1日24時間であり、お金と違ってそんなに大差がないと表現できます。毎日人類には24時間という同じ財産が配られますが、その使い方には大きな差が表れます。いわば、その人の普段の生活(ルーティーン)に本質が表れると言うことです。
ムダなことをすることは、平等に与えられた資源の損失です。「何をするのか?」については個人の性向に寄るかもしれませんが、逆に「何をしないか?」の意思決定がしっかりできている人はその人の価値観の大部分を決定づけているかのように感じます。
時間が無限にあれば、無駄なことをしても別に構いません。限りある命を有益に使うために、自分の「しないこと」を具体化した人を評価してもいいのではないかと、強く感じています。
やっぱり私の仕事の「採用面接」に、活きそうなんですよね。
★
もう一つ気になったテーマが「友人」の考え方です。この考え方も、結構面白い。
「フレンド申請」という言葉がそれほど違和感なく浸透していますが、筆者はそれは「おかしいこと」としています。友達の定義は「偶発性」と「反利害性」に成り立っており、申請という行為は「偶発性」を欠いていると。…なるほど。
確かに友達のきっかけは自然発生ですから、覚えていないことがほとんどですよね。小学校のクラスとか、大学ゼミとかまぁ偶然性の一部です。大人になってからの友人が少ないのは、そういう意味なのでしょう。
会社の人も「偶然性」は生じていますが、そこに「反利害性」が加わらないので友人ではなく「同僚」というカテゴリーに入ることが大半です。わかりやすい。
利害が絡む人を「友達」とするのは確かに違和感ですし、こちらとそちらの意識が一致するとは限りませんよね。日々の生活が固定化されて「偶然性」が減り、新しく知り合う人は「反利害性」を満たさない。だからこそ大人になって「友達が出来ない」ということが、誰しも悩むことなんだと思います。
それに加えて「仕事」や「家庭」で多忙になることもありますし、思考が確立してきて新しいことへのチャレンジも億劫になってくる…。そりゃあ新しい友達なんて、ハードルはどんどん高くなるわけです。
★
「老人」や「友人」という他人の考察において、本書では「品性」という解釈も面白かったですね。これで、最後にします。
「品の良さ」って言葉にするのは難しいと思ってましたが、一言「欲望に対する速度が遅い」と定義されていました。これは決して煩悩を振り払ったお坊さんの様な人、いわば「欲望が無い」というわけではない。
期待していることが実現するとはあまり思っていなくて「いつか叶えばいい」とか「別に叶わなければ仕方ないよね」というぐらいのスタンスで、のんびりとしている人を「品が良い」と定義していました。この辺は、タイトルの「絶対悲観主義」が強く出ているところです。
欲望達成という「ゴール」だけでなく、その「実現プロセス」も楽しめる人は確かに多くない気がします。みんな欲望に真っすぐで、最短距離を効率的に目指したいわけですから…。
「潔さ」を持っていて「得られる選択肢の全てを選ばない」という観点も、現代の「効率化」が叫ばれる世界では、好印象です。意思決定がはっきりしていて「とりあえず持っておく」の様な、保留癖がない。持たないことを「善」とするミニマリスト思考とも、言えそうです。
例えるならバイキング料理で何でも取ってきて、結局ただ腹を満たすような人とは真逆の様なものです。つまりは、取捨選択が潔い。
人間関係においても「嫌いな奴から嫌われたい」というスタンスだそうですが、これは確かにもっともだと思いました。うんうん。
…③で終われそうです。最後はビジネス関係のまとめをしていきます。この本は、面白いですよ。
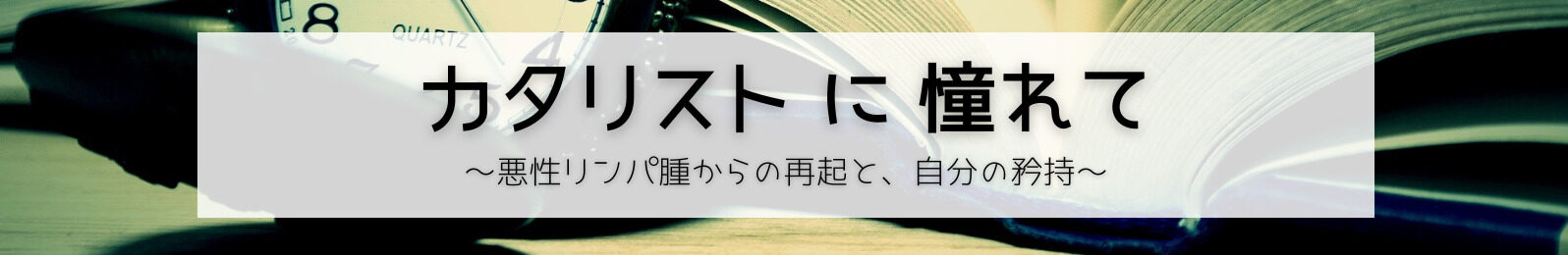
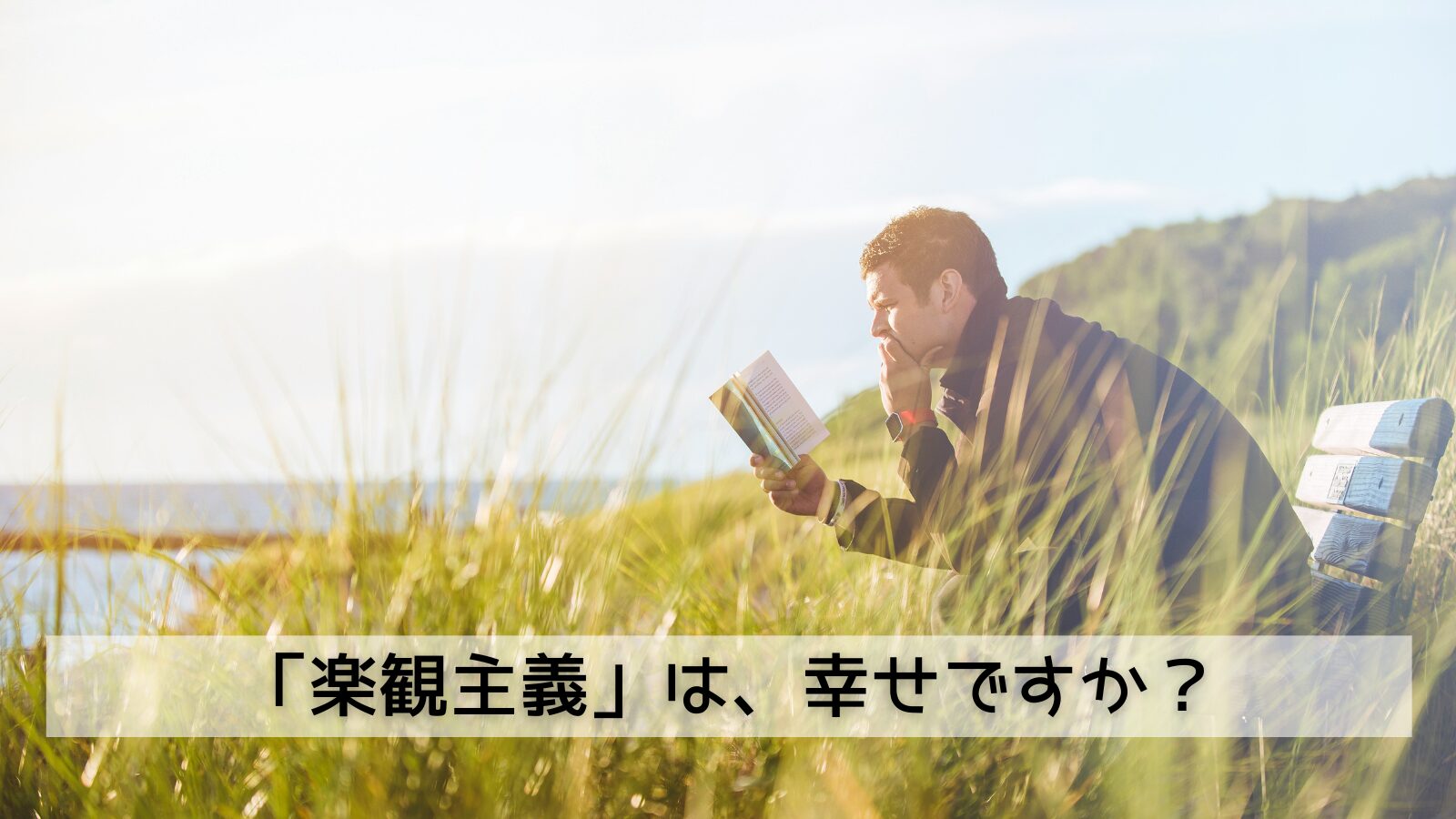
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/43ded940.c5c16099.43ded941.cac05dcd/?me_id=1213310&item_id=20670403&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9327%2F9784065289327_1_2.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)


