最後のまとめです。ビジネス関連の情報を中心にまとめました。
「仕事」を本書では「自分以外の人間に価値提供すること」と定義づけています。仕事は「他人のため」であって、自分のこと(満足感など)はあくまで二の次だという解釈ですね。「自分の満足する仕事が出来ればそれでいい」なんて話も別の本ではありましたが、この解釈は私も賛成の立場です。
自己満足を追うのはあくまで「趣味」であって、あくまで「仕事」においては他人の評価が大事なわけです。自己満足ではダメで、相手のニーズを捉えているかに重きを置くことが推奨されています。
そう考えるとブログ記事を「自分の書きたいこと」とすべきなのか、はたまた「読み手の読みたいもの」とすべきなのかの議論は、多分決着することはないでしょう。
ただ、私は「ターゲット顧客の選定」と言う観点においては、この考え方はとても重要だと思います。具体的なターゲットを絞れば絞るほど、該当しないターゲットも増えていくことは避けられないからです。
いわば、ターゲット外の人たちから「ちゃんと嫌われているか」がポイントになるかと思います。これは「嫌われに行く」という感覚よりかは、結果的に「正しく嫌われる」と言う表現がしっくりきます。
「みんなに好かれる」という前提での仕事は、結局誰にも響かないですし誰のためにもなっていないことがほとんどです。毒にも薬にもならないことをするのではなく、特定の人に好かれる(そして結果的に得敵の人に嫌われる)仕事ではないと、意味がないということですね。
コロナ下で破壊されたものは「会社には行かなければいけない」という「習慣」であると、一文記載がありました。本能的に「満員電車に乗って、会社に行きたくないなぁ…」と感じていながら出勤する習慣が破壊された、珍しいケースであると言えるでしょう。
リモートワークがもたらしたのは「効果」と「効率」のトレードオフであると言えます。対面では「効果」があるかもしれない(と言われがち)ですが、オンラインでは「効率」に圧倒的な軍配が上がるのが自然です。
タイパやコスパが叫ばれることにどこか違和感を感じがちな人は、つまるところ「効果がないことをどれだけ効率的にやっても、意味がないんじゃないの?」という感覚なのではないかと思います。「効率」を重視した結果、逆に「効果」を失えば無意味ではないのかということです。
私はどちらが正しいかは、結局のところ「成果」に左右されるのではないかと思いますが、リモートワークの白か黒かという議論はそもそもナンセンスだという結論が本書です。あくまで「働き方の選択肢」でいいということですね。
リモートワーク「だけ」とか、絶対に「出社」と白黒つけるから軋轢が生まれるのであって、選択肢としてどちらもOKという状態が望ましいという結論ですね。どちらかしかダメだから不満が出るのであって、どちらが都合が良い(会社にも、個人にも)のかは「成果」を基に決めるのが理想的だと思います。
人間の感情的に、AIから聞くことは正しいとしても受け入れがたいところは消えない気がします。病気のことは医者から直接聞きたい(AIだとちょっと…)と思いますし、自分が会社の社長だとしてAIから「あなたがいなくなることが、会社の利益です」と言われて受け入れられる人が果たしてどれくらいいるのか…という話です。
それが、正しい…としてもです。
★
最後の最後は「会社組織」についての、まとめです。「組織」と「チーム」についての考え方をかなりシンプルに記載してくれていました。
「組織」づくりについては、自分としても仕事で取り組むことは多いです。組織の定義付けとしては「システム的なニュアンス、仕組み」とされていました。一言で言うと「ルールや仕組み」という最後の拠り所のイメージです。
一方で「チーム」は「実際の業務を行う集合体」という位置付けです。実際に業務をするのはチーム毎がほとんどであり、チームは「組織の部分集合」とも言えます。
言葉として似ている2つですが、実態は大きく異なります。会社組織の中には大小様々なチームが存在しますが、結論として「因果関係が強くない」ことが面白いところです。
会社組織が最悪だとしても、優秀なチームは存在します。一方で最高の組織状態でも、うまくいかないチームが存在する。いわば「組織を何とかすれば、チームも改善される」ということは、都合の良い幻であると言えるでしょう。
改善業務の主体は「組織」になりがち(ルールをメインに対応しがち)ですが、これは以前は組織の方が「仕事の意志において重要な位置付けだった」と言うことが伺えます。今でも「上が決めないと動けない」という企業文化は、この考えが色濃いのだと思います。
一方で現在は明らかに「チーム」の方が重要です。情報伝達がツールの発達によって容易になり、分業が難しい(その場その場で対応が求められる)状態では組織の意思決定を待ってはいられません。変化の速度が著しい現代では、流動性を重視して「チーム単位」での柔軟な対応が重要になっています。
では「組織」は不要なのかと言うと、そういうわけではありません。前述の通り「組織」は困った時に最後に頼る場所であるからです。ただ、仕事単位上チームへの「権限譲渡」は避けられないことになるでしょう。
普段は「チーム」が大事になるのは、もう変えられません。優秀な「現場責任者」を育成して、状況に応じた指揮命令をさせられる小回りの利いた企業が、今後の時代をリードしていくことになります。
…だいぶボリューム感のあった「絶対悲観主義」も、ようやく一段落です。読書はだいぶコスパのいい趣味だと思いますが、情報を無料で手に入れやすくなった昨今では、1冊の本を1,000円以上費やすことが「コスパが悪い」と揶揄されることもあるようです。
本に関してはサブスクを使わずに1冊を大切にしたい(動画サービスとは違う)自分としては、その感覚はあまりありません。250冊は少なくとも読んできた自分としては、読書習慣の定着はかなりおススメなのですが…。
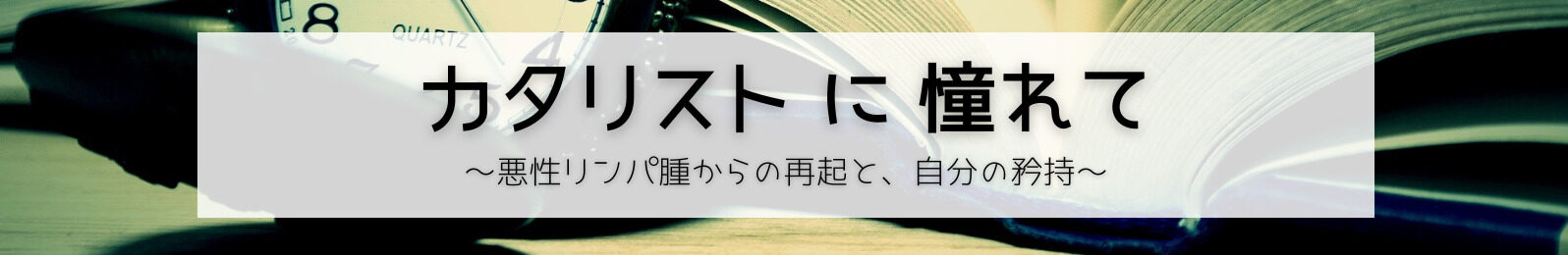
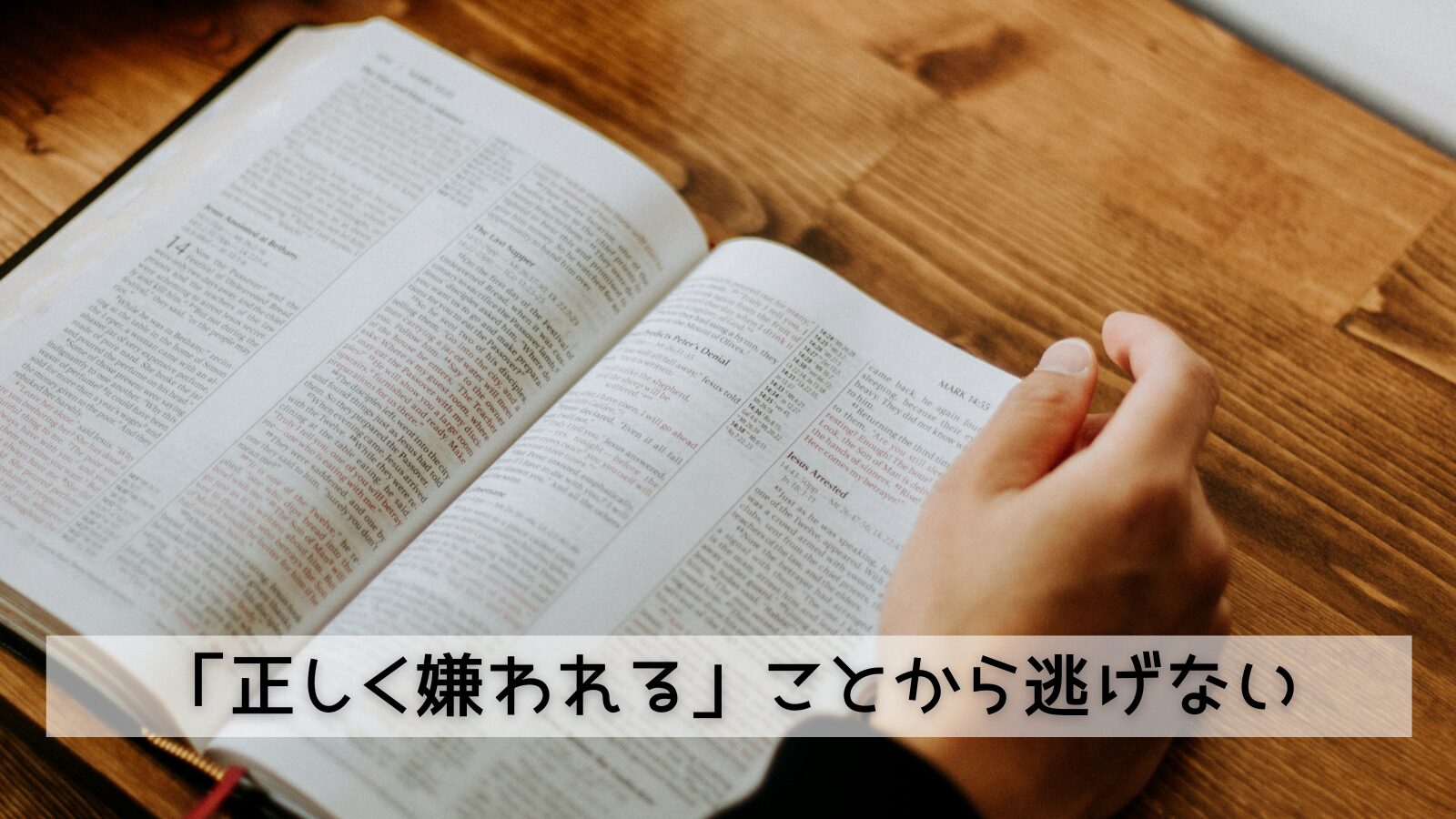
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/43ded940.c5c16099.43ded941.cac05dcd/?me_id=1213310&item_id=20670403&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9327%2F9784065289327_1_2.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)


