今日ご紹介するのは「絶対悲観主義」になります。これは…読みごたえがあって、面白かったですね。学ぶことも多くて、本当に目からウロコでした。
「悲観主義」と聞くと、あまりいい印象ではないかもしれません。対義語の「楽観主義」を推奨している話の方が、一般的です。
しかしながら「楽観主義」の本質は「まぁ何とかなるさ」という「期待」です。「うまくいくだろう」という期待が、自分たちの行動を制限しているのではないか?という考察が、私にはとても面白かったわけです。
悲観主義のメリットは、抽象的に5つです。
1つ目は「仕事が気楽にスタートできる」と言うことです。楽観主義のゴールは、当然「成功」です。言葉だけを捉えれば、確かに一歩目を踏み出しやすそうに感じます。
しかしながら、悲観主義の本質は「成功」ではありません。うまくいかないゴールを想定しているので、私個人としてはそちらの方が物事を始めやすいのではないかと強く感じました。
…うまくいかなくて、当たり前なんです。
2つ目は「リスク耐性」になります。悲観主義は慎重ですので、計画を立てます。細かく精査します。楽観主義は「なんとかなる」ので、そんなことしません。でも、実際は計画通りにいくわけないので様々な面倒ごとが起こります。それこそが平常運転なので、繰り返していくうちにリスク耐性が自然と高まっていきます。
言葉では「悲観主義」はなかなか行動できない様に感じますが、それは「成功」を思い描いているからです。本物の悲観主義は「成功」なんて期待していないので、計画は綿密ですが障壁はありません。「どうせうまくいかないだろう」なんですから。
3つ目は「先を見通す力」です。緻密な計画の中で、イヤでも様々なケース分析を行います。「こうだったら」「こうなったら」「でも…」というシミュレーションを行いますが、大体のことは起きません。
一方でこの積み重ねは、様々な計画に応用できます。抽象化の能力が自然と高まるので、物事の本質を掴んで個別具体に当てはめていけるようになるわけです。
4つ目は「顧客志向」の視点です。営業職にとって、この悲観主義は大きなスキルになると思っています。長年顧客対応をしてきましたが、自分の思い通りになることは「ほぼない」と断言できます。悲観主義ではそれが当たり前なので、別に恐れることはありません。
「どうして、うまくいかないんだろう…」という悩みは、そもそも「これならうまくいく」という間違えた期待から、産まれたものであった…ということです。顧客は、自分の思い通りになんて、いくわけありません。
5つ目は「本当のスキルの発見」です。これだけうまくいかないと思いながら色々やっていると、なぜかうまくいってしまうことがどうしても起こります。不思議な日本語ですが、自分の意志とは別に「うまくいってしまう」わけです。
これこそが自分の「才能」であると言えます。自分の中で見えにくい、そして勝手にあると思い込んでしまう「才能」の正しい本質をあぶり出してくれるのが、この「悲観主義」になります。
失敗を「平常運転」と捉えられると、行動回数が増えることが大きなメリットです。ただ、失敗にも深さがあって、ダメージを受けてなかなか立ち直れない時も当然あるわけです。
その中で本書では「本当の失敗後に、自分で対処など出来ない」と断言されています。ここまで潔いと、脱帽です。
とことん自分に、期待していません。
そもそも人間には「自然回復力」が持ち合わせされているので、それまで「黙って待つ」ということが最善であると、本書にあります。
確かに過去の痛みや苦い出来事も薄れていくわけですし、自分で挽回できる能力があるのならなら「そもそも失敗してないだろう」と開き直った方が、精神衛生上良さそうです。
自分の「何とかしよう」になんて期待せずに、ただただ時を使いましょう。人によってはその時に「正論」をぶつけてくるのかもしれませんが、正論に従ってもうまくいくとは限らないわけなので、ただただ「時」を使う方が無難であろうと腹落ちしました。
時間は、偉大です。
★
本書では「幸せ」について、多くのページ数が割かれていました。ピックアップしていくと幸せには二通り(微分派と積分派)という内容が、印象に残っています。
「微分派」とは、直前との差分で幸福を感じるという特徴があります。逆に「積分派」は、積み上げてきた総量に幸せを感じるという特徴です。
世の中の印象としては「微分派」の方が、イメージしやすい様に感じます。「ボーナスが入った」「彼女が出来た」「新しい車を買った」といった出来事の、直前との「差分」が幸せを生みます。
「ボーナスがない」「彼女がいない」「車が古い」といった状態と、瞬間的に比較することになるので、インパクトは大きいでしょう。
デメリットは、結局「日常」に収束してしまうことにあるかと思います。その瞬間が最大値であり、その状態が長く続くことはありません。人間は刺激に慣れてしまうので、次回の幸せを感じるにはより大きな「刺激」が微分派には必要です。
一方で「積分派」は、積み上げてきた幸せの総量が主です。特徴しては「気づきにくいが廃れない」といったイメージでしょうか?
「楽しかった思い出」や「子育ての喜び」といった、後から振り返ってしみじみと幸せを感じるイメージです。瞬間的に何かに気づくことは難しいですが、積み上げてきた日常に幸せを感じることは往々にあります。
…その機会が多くなったのは、私が病気をしていることも要因かもしれません。
両者の違いは「ベストセラー(瞬間的)とロングセラー(総量的)」や「流行語大賞獲得の人気芸人(瞬間的)と長年テレビのひな壇にいる芸人(総量的)」の様に、私は捉えています。どちらが良いのか…ということについては、皆様にお任せします。
★
出来事に対して「どう」思うのかは、結局は自由です。ある人から見れば悲惨な出来事も、別の人から見れば「チャンス」になることは往々にしてあります。
例えば「飛行機の遅延」は、急いでいる人には「悲劇」ですが、旅行を少しでも長く楽しみたい人にとっては、喜ばしいことかもしれません。「管理職への昇進」は給与が上がることをプラスに見える人もいますが、逆に「責任を負わされたくない」と悲観的に捉える人もいるでしょう。
物事は捉え方次第なのですが、傾向として「不幸」は見えやすいことが多いです。不満や不足など「足りない」という視点は、目につきやすいのが大きな理由です。1,000ピースのジグソーパズルのうち、3ピース埋まっていない状況を想像してください。
…埋まっている997ピースと、足りていない3ピースの隙間はどちらが気になるでしょうか?そういうことです。
不満は目に見えやすいので、幸福を目指す時にやりがちなのが「不満を取り除く」ということです。結果的にそれは間違いで、それでは幸せにはなれません。
不満を取り除いた状態は「没満足」にしかならないからです。
見えやすい「不幸」への対処をするのではなく、見えにくい「幸せ」に気づくことをする必要がありますが、多くの人はそれをしません。「幸せになりたい」は少し違っていて、本当は「幸せになりたい(けど、面倒なことはしたくない)」が本音なのだろうと思います。
「ホームランは打ちたいけど、きつい練習はイヤだ」というプロ野球選手に、何を言ったら委員のでしょうか…?
だからこそ簡単に幸せになれる(なれた気がする)ことが、世の中から無くなりません。「疑似幸福」とても、読んだらいいでしょうか?
そもそも幸せは相対的なものであって、分かりやすいのは「他人との比較」が挙げられます。時代や年代、性別等を加味して「比較しやすいモノ」を比較して幸福か、不幸かを判断するのが一般的です。
「誰かの不幸や不満を言う」や「有名人のゴシップを見る」は、自分の現状を好転させることは、一切ありません。ただ、それが無くならないのは、自分が「相対的に幸せな気がする」という一種の感覚マヒの様なものです。
…お手軽に、労せずに「疑似幸福」を味わえるから、無くならないんです。
本来は「他人の幸福」は、自分の幸福とは無関係です。「悲観主義」はそもそも他人と自分を切り離して考えています。
多くの人は比較対象が身近な人やモノであるからこそ、勝手に自分と比べて幸か不幸を並べているのですが、例えば大谷選手の給料が一億円増えてもなんとも思わないでしょう。…比較対象が自分から遠すぎて、イマイチ関連を見いだせないからです。
悲観主義の捉え方は、まさに常々そんな感じです。「他人は他人」や「自分が他人に影響を与えられるわけがない」という冷めた目線でいるので、普通の人が参加している無価値なラットレースから抜け出している状態です。
別に何かの手段がなくても、比較対象がなくても、自分で定義づけた「幸せ」という目的は達成できることに気づかされます。
…ながくなりましたが、まだ半分も終わっていません。それだけ「読み応え」のある本でした。続きは、また後日。
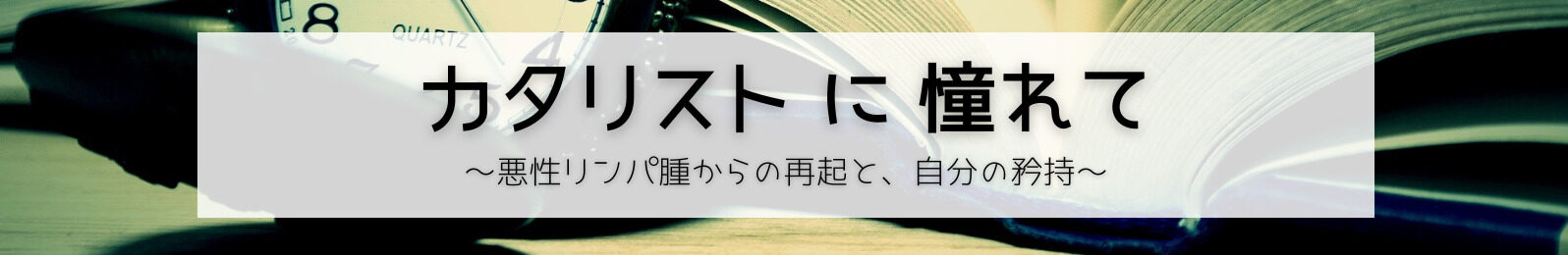
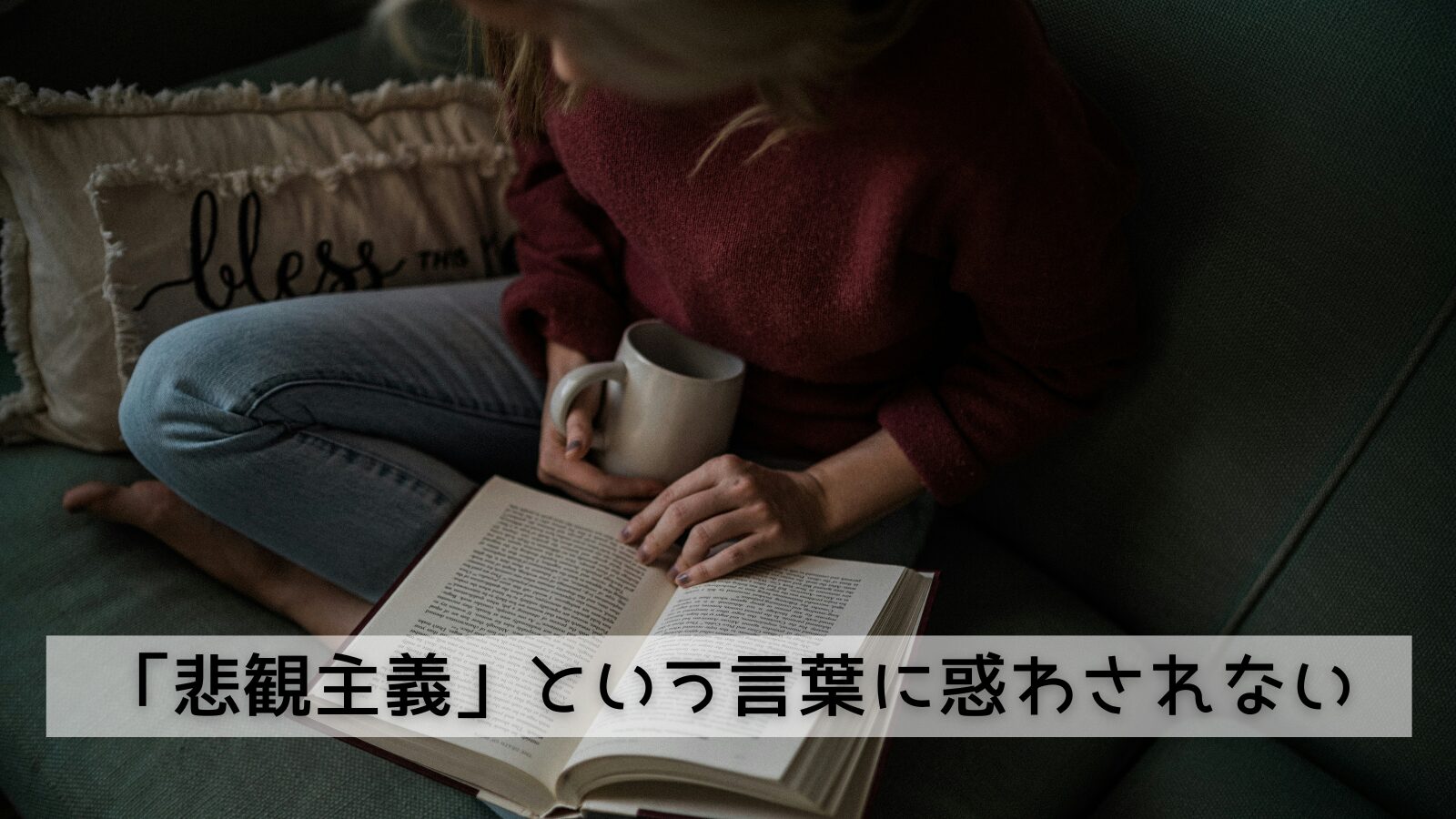
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/43ded940.c5c16099.43ded941.cac05dcd/?me_id=1213310&item_id=20670403&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9327%2F9784065289327_1_2.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)


