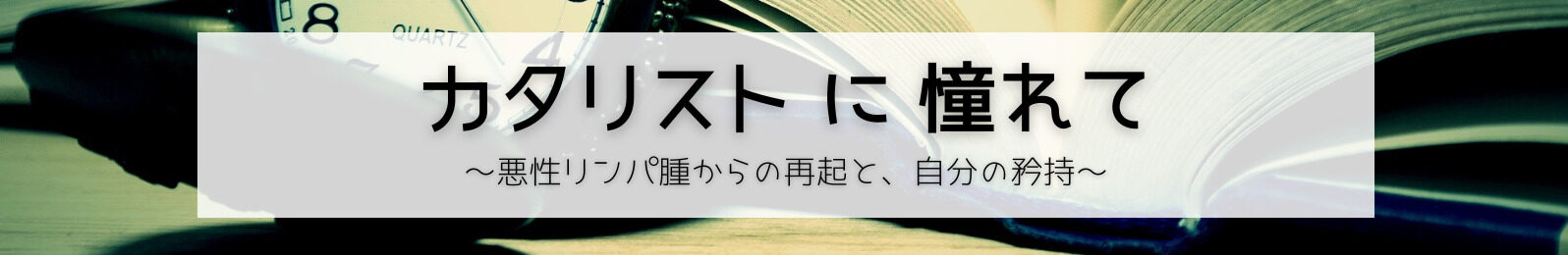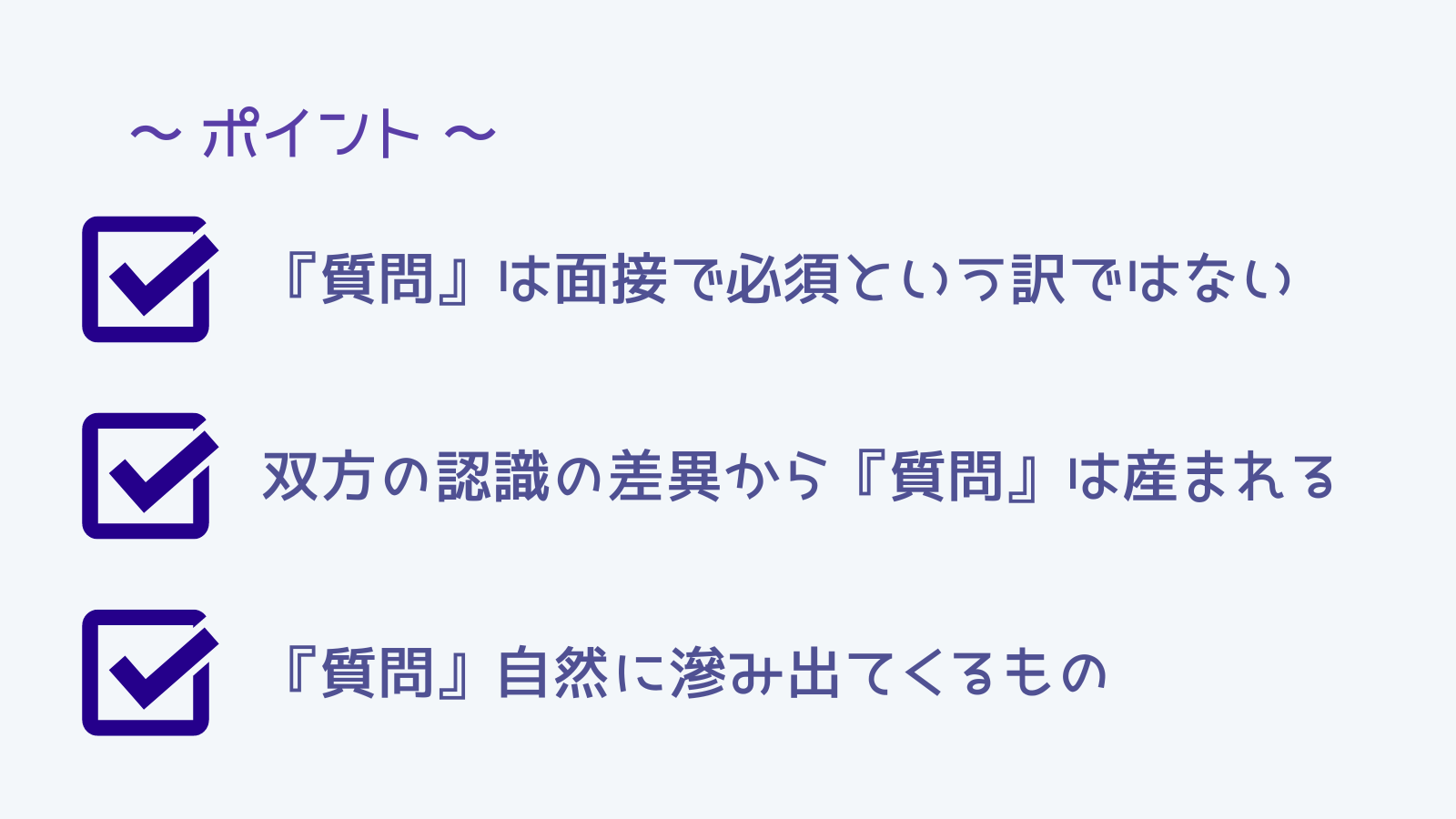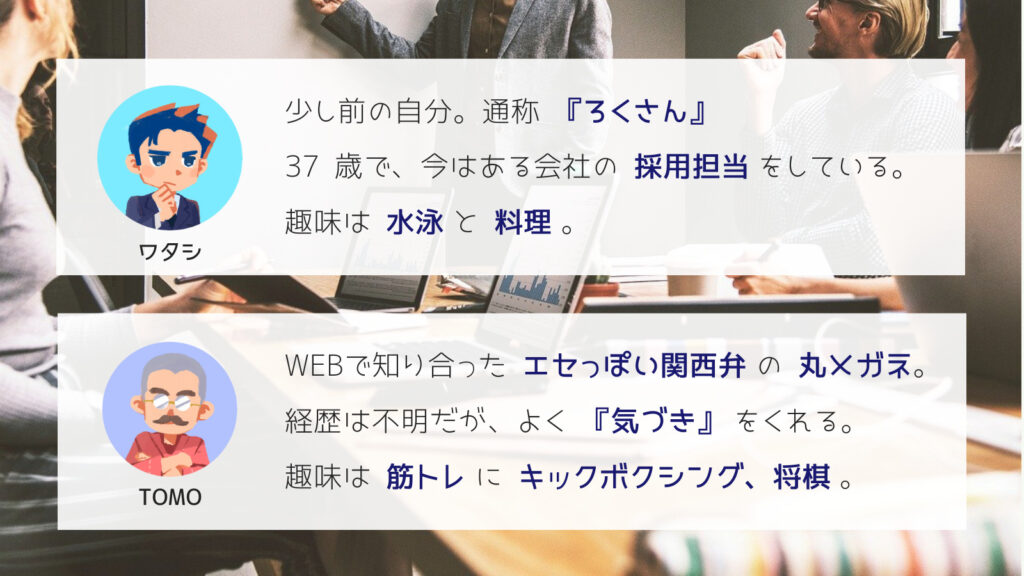

今年は大学生の採用で、何人ぐらい面接したんや?

今年は今のところ、15人ぐらい面接してるよ。

15人かぁ?
結構な数やな。

まあ、それが仕事だからね。

で、会社に合いそうな人材は見つかったんか?

うーん。まぁまぁってとこかな?
でも。評価している学生の中に「ちょっと引っかかる学生」がいてさ。

…引っかかる?

うん。

どういうことや?

面接全体を通して印象はすごく良かったんだけど…。
最後の質問でちょっとね。

質問?

ほら、「最後に何かありませんか?」
みたいに聞くじゃん?

あぁ、あれか。
それがどないしたん?

その時に出てきた質問が、割と面接中に何度も説明したり確認したりした部分だったから…。
「なんでわざわざそんなこと聞くんだろう?」って、面接官が全員思ったみたいでさ。

あー。
なるほどな。

なにか分かるの?

きっと『質問の本質』を理解していない学生だったって事ちゃうかなと。

質問の本質?

そもそも『質問』って、どういう行為やと思う?

行為?
えー、難しいね。

「質問」ってのは…。
『自分と相手との認識の差を埋める行為』やねん。

まだまだ難しいなぁ…。

学生と会社側との間に「会社についてどこまで知っているか」っていう認識には、当然隔たりがあるやろ?

まぁ、そうだね。
当然かな。

だから質問を通じて「隔たり」の部分をもちろん完全にとは言わないけども、少しでも埋めていく…みたいなイメージやね。

なるほどね。
でもそれが今回の件と、何か関係あるのかな?

極端に言うとやで?
自分も相手も『同じだけ認識』していれば、隔たりはないから『質問』って出てこないやろ?

そうだね。
となるとその学生は「必ず何か質問しなきゃいけない」っていう使命感だけで、質問していたんだろうな。
だから。内容がちぐはぐになってしまったんだ。

きっとしっかり準備してきていて、「質問を話すこと」が目的となっていたんやろうな。

そうかぁ…。
彼は、どう評価すればいいかねぇ?

そもそも「面接」って、企業側からもたくさん質問するやろ?

そうだね。

「なんでうちの会社を希望した?」とか、「強みは?」とか、「どうして強みなのか?」みたいな事聞くやんか?

うん。

「質問」ってそもそも用意するものじゃなくて、『自然に出てくるもの』やねん。
認識の違いがあって、そこの差を埋めるために自然と聞きたくなるものであるべきやねん。

…確かにそうだね。

企業と学生との間には、何かしらの隔たりは基本的にあるものや。
ただ、面接中にいろいろな情報を得て、その隔たりが必要なところまで埋まるってことはよくあることなんよ。

となるとその学生は『質問』がしたかったんじゃなくて…。
『質問っていう義務を果たさなきゃいけない』って思って、発言しただけってことかなぁ?

まあ、恐らくそうやろうなぁ。
『質問は必ずする必要なんてない』のにな。

…どう評価したら良いかなぁ?

難しいところやけど、全体を通して問題がなかったんやとしたら通過でえぇんちゃう?
そして次の面接の最後に、質問を聞く時には「もし無いなら無いでかまわん」ってちゃんと言ってあげた方が、彼だけじゃなく候補者のためなんじゃないか?

そうだね。次はそうするよ。
『質問という行為が目的にならない』っていうのはちょっと大事だね。