続きになります。参考資料は10冊以上読んだこともあり、内容は多岐に渡っている印象です。一方で本質的な軸はあまり変わっていない印象も受けており、ある程度簡易にまとめられたという感覚も持っています。
4 時間と効率のマネジメント
私が学び始めた時の会計学には、ある一時点を捉える「切り取り」の要素が強かった気がします。実際に金融機関で働いていた時に目にしていた決算書は、あくまでその時点の企業の実体の近似値でしかありません。しかも、その決算が出来上がるのは実際の決算日から3ヶ月程度経過した時間のズレが生じています。
しっくり来たのは会計学に「時間」という概念が、具体的に入って来てからと認識しています。単純なお金のやり取りだけでなく、そこに時間の概念が加わることでとても深みのある解釈が生まれました。
売上ー費用=利益という方程式が、私は嫌いです。費用が売上に本当に貢献していたか、わからないからです。時給と言う概念が、私は嫌いです。給料は顧客満足から生まれるものであり、時間内に行った労働が本当に付加価値を生んでいるかは分からないからです。
労働に時間の概念を持ち込むことで、付加価値を生んでいない労働に割いている時間を可視化することが出来ます。「忙しい」が顧客満足に貢献していないのであれば、それは無駄に動いたことの証明です。極論を言うと「寝ていた方が良い」とまで言えるでしょう。
労働時間に対して、生み出した付加価値をもし完全に可視化することが出来る世界になれば、人件費に悩むことは無いのではないかと思います。世の中から不公平感を取り去ることが出来る…のかもしれません。まぁ、難しいというかムリでしょうけど。
売上高をもっと「顧客満足への貢献度合い」と捉えて、自分の仕事を「そのためにどれだけ貢献できたか?」とすれば、単に時間を不要な労働に忙殺されることは少なくとも減ると思います。成果に繋がらない「時間」も「コスト」もいかに最小化するのかに対しては、やはり会計学の考え方は重要であると再認識する次第です。
目的があれば、会計学は有効な手段の一つです。
5 損得判断と意志決定
意志決定をする上でも、具体的な金額にして可視化することは大切であると考えます。特に過ぎ去って変えられない過去の事実に固執して、将来の意思決定を誤らないことは企業でも個人でも無視できません。
人の判断において、目に見えやすいことや印象深いモノに引きずられがちであることは、十分注意する必要があります。例えばコンビニにおいてあまり値引きがされない事例は、廃棄をすることの方が値引きをするよりも将来のキャッシュフローを増やす事例として挙げられています。
値引きをすることによって購入されない定価の商品、値引き後の商品を陳列することによる他の商品を販売する機会損失を考える…といった複数の視点が必要になります。分かりやすく「捨てるなら安くしてでも売った方が良い」というだけでは、問題解決にならないのが面白くもあり難しくもあるところです。
日常生活においても、この視点は結構重要です。欲しい商品が1万円だとして「先週は8千円だったのに…」となるようなことは、よくあるかもしれません。逆に1万円で先週購入した商品が「今だったら8千円なのに…」というようなことも然りです。
「過去や現在の時間軸を混同せず、今の時点で最善の選択肢を考える」という視点が最も大切であり、それに加えて「意志決定に影響を与える可能性のある選択肢はないか?」という姿勢も大切です。この2つが日常生活でも企業の意思決定でも混同、錯綜している実態があると思います。ホント、よくあります。
いわば意思決定において、間違えた情報や選択肢によって最適ではない選択をする可能性を孕んでいることに注意が必要です。悩んだり考えたりしないことを捨てる一方で、必要な情報の確認も怠らないことが大切ですね。
6 経営戦略と方向の改善性
ここまで会計視点でいろいろと述べてきましたが、最も多い引用が「売上は顧客満足によってもたらされる」ということになります。これは従来の会計学が効果を発揮していたとされる経営改善を可視化する目的に対して、とても有効であると捉えています。
「ムダを探すための会計」や「銀行に出すための会計」になりがちではありますが、そこに「顧客満足度」を加えることでいかに「顧客満足に関係しているか?」を戦略的に考えることが出来る様になりました。売る側の都合で値上げやコスト削減がされがちですが、それが顧客満足を下げることであれば基本的に愚策であるというシンプルな価値観が私は好きです。
一時的な売上改善は見込めたとしても。長期的なマイナスを導く施策は企業にとってマイナスでしかありません。一方で、会計学がそのように使われることが多い事実も否定はできないのが残念なところです。
結果的に会計学は、家計でも企業でも「目的」ではなく「手段」であるべきと捉えています。顧客満足を前提として、そのために「どうすればいいのか?」「どう改善するのか?」を金銭に可視化することこそが会計学の本質でしょう。使い方によって毒にも薬にもなる一方で、使う目的が曖昧にされがちな会計学。やっぱり面白いですね。
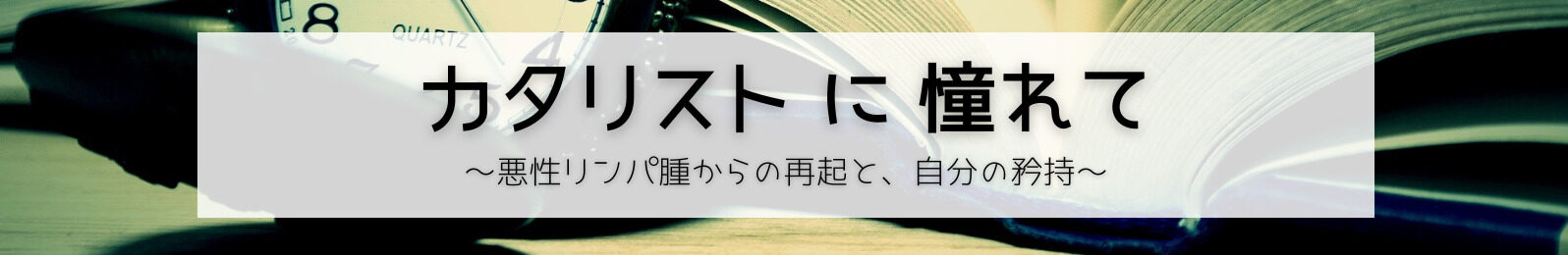

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45330b1f.368f98cd.45330b20.29ea5a4e/?me_id=1278256&item_id=13072487&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5465%2F2000001715465.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


