メンタル管理において、自分の中で1冊選ぶならこの本だと思っています。モヤモヤを言語化してもらえましたし、シンプルで考え方もわかりやすいです。この考え方こそ「瞑想」や「マインドフルネス」だと思っています。
内容は、さらにシンプルに自分が共感したところを中心にまとめました。おススメしたい本ですので、こちらはぜひ。
心の反応を、複数に分けています。その中でも「感覚」「感情」「思考」に注目します。人間が大きく左右されるのは「感情」と「思考」になります。
「快」や「不快」という「感情」によって人は左右されますし、日々の「不安」や「心配」は自分の「思考」が原因です。そういった「心の反応」が起きた際に、心の反応の「対象を変える」という考えが、目からウロコでした。
「感情」や「思考」が起きた際に、その反応を「感覚」へ置き換えて集中すると、心がとても落ち着くことになります。この感覚の意識を「マインドフルネス」と私は捉えています。
その際のポイントは、「ただそこにある」という「存在」に着目することになります。肯定も否定もせず「ただそこにある」とか「イマ○○である」という解釈をすることが、自分を解放することになるわけです。
「瞑想」や「マインドフルネス」への期待は、どちらかと言うと「ネガティブな感情からの脱却」にあるでしょう。欲求を満たしているというよりかは、苦痛の無い状態です。苦痛は自分の「思考」や「感情」が生み出しているので、そこから離れて今の「感覚」に焦点を当てることが大切です。
「私は~である」というただの「状態」や「存在」として認識するだけで、自分の「不快」から離れることが出来ます。自分で自分をただ苦しめていただけであると、気づけることが出来たのはこの本のおかげです。不快という「感情」を「現実」にラベリングしていただけで、事実には何も意味はありません。逆に「快感」とラベリングすれば、その現実はその通りになります。
「万事、塞翁が馬」とは、本当によく言ったものです。
不快な感情の代表として「怒り」があります。怒りには様々な理由があり、「その方がラク」「正当化」「プライド」など様々です。ただそれも先ほどと同じように怒りの原因である「事実」がただ存在していると考えるだけで、だいぶコントロールできるようになりました。
現実において変えられることは多くないですし、世界情勢や日本経済も自分も力ではどうすることも出来ません。どうしようもない人も、この世にたくさん存在してしまっているんでね…。
気になったところを、もう一つだけご紹介すると「意欲」についてになるかな?と思います。…新年に立てた目標は、なぜ挫折してしまうのでしょうか?
「意欲」には様々な種類があり、やる気を維持できる人はこの切り替えが上手と言うのが新しい学びでした。「単純なやる気」「憧れ」「ワクワク感」「気合と根性」の様に異なる「意欲」を状況に応じて使い分ける、切り替える必要があるなんて、考えたこともなかったですね。
ただ、本当に自分に必要なモノは「意欲」からは離れたものであるという視点も、面白いと感じました。「呼吸」なんて飽きることはないですし、いちいちそのことを思い出したりもしません。
継続の意欲って、結局その人個人によって変わるモノですし、呼吸のレベルまで達してしまえばそんな「好き」とか「やりたくない」という感情によって左右されないのだなぁ…としみじみ思いました。
他にも自分の様々な感情の取り扱いについては、様々なケースを分析して記載してくれていました。ただ、やっぱりメインどころは「ネガティブ」の取り扱いについてだと思うので、そこにクローズアップしてご紹介しました。
今は感情が揺れ動いた時には「呼吸」を基本として意識を「感覚」に集中していますし、眠れない時も「呼吸」に「皮膚」、「温度」といった感覚に集中することで事前と眠れるようになります。
これが出来るようになった時に「瞑想」や「マインドフルネス」における「イマ」に集中する効果を実感することになりました。
イマ、生きている。その実感が、自分をとても幸せにしてくれます。この感覚を、共感してもらえると、嬉しいです。
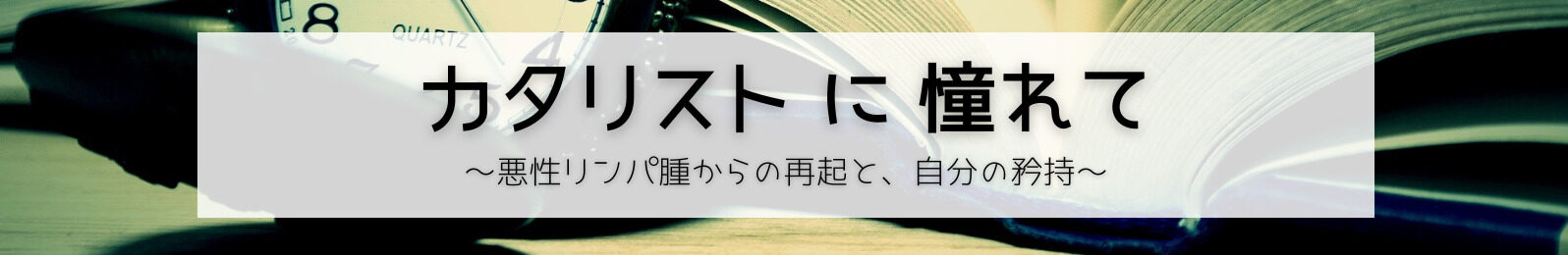
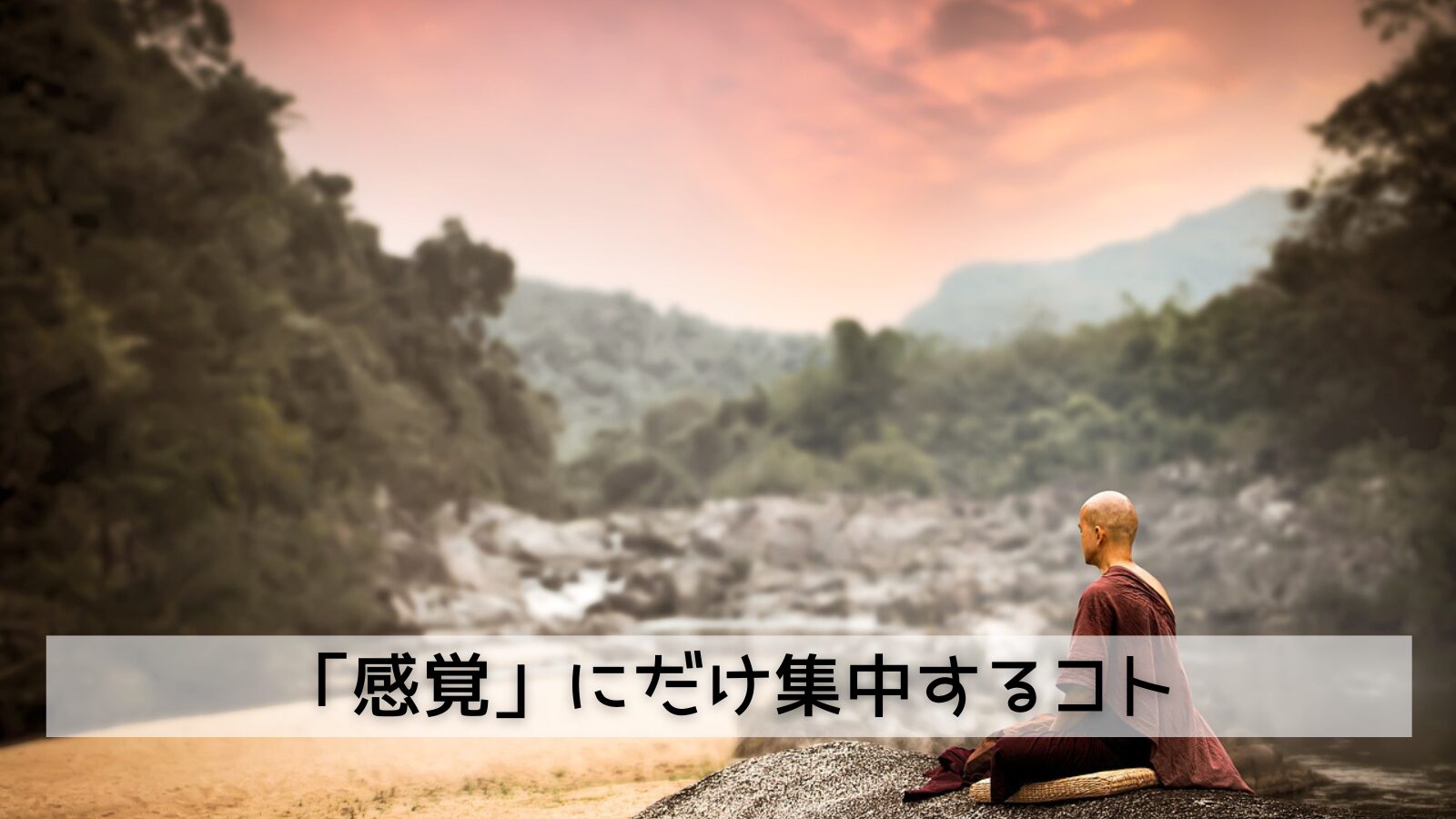
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/43ded940.c5c16099.43ded941.cac05dcd/?me_id=1213310&item_id=17866071&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fcabinet%2F5389%2F9784046015389_2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


