仕事を進めていく上で、事前の「情報共有」ってめちゃくちゃ大事だと思っています。私は「後からの手直し」が大嫌いなので、なるべく始める前に方向性のすり合わせを行いたいタイプです。
…が、結局うまくいくことはほとんどありません。「もう一人でやるからええわ!」となることも多いのですが、一人で出来ることと、複数人で出来ることは結果的には量が違います。
ですので、出来るだけ事前の情報共有を言語化するためにいろいろと仕入れた情報の中で、最も端的だと感じたのがこの本になります。
非常に分かりやすいですし、仕組み化もしやすいと感じた一冊です。
自分一人であれば「とりあえずやってみる」と「やりながら修正する」が大好きな私ですが、誰かに仕事を頼むときはそうはいきません。ですので、当面の「目標」を定めることを第一に設計を開始していきます。
「考える」という行為は「全体像を具体的に可視化していくこと」と「問題点とその対策を見つける」と定義しているので、全体像を大型の用紙やマインドマップに記載していきます。最初の内は「深堀り」というよりかは「水平」をイメージして、様々なポイントを書き出していきます。必ず必要になるポイントは「全体像」はもちろんのこと、関係者(人)と時間軸(時間)の整理ですね。
5W1Hをベースにして様々な情報を集めますが、時間軸(今大事なこと)や関係者(~の立場なら)を加味すると、結構情報の集まりが違うのでおススメです。前述の「考えている」の定義から外れて「悩んでいる」人が多いのも、この作業中に良く気が付きます。
ですので「全体像を具体的に可視化していくこと」と「問題点とその対策を見つける」という具体的な行動が出来ないのであれば、「時間の無駄」なので一旦その場から離れていた方が生産性が良いですね。
これを第三者に伝える時に注意しなければいけないのは、話している「視座」がズレることだと思っています。大まかな内容を決めている時でも、ずいぶんと深いところや細かいところを考えている人がいます。間違えている訳ではないので指摘しにくいですが、話のステージがズレていると話が進みません。
特に「時間軸」がズレていて、「イマ」どうするかが話し合えていないことや「~があったらどうする」の様な限りなく0に近い(でも起こることは否定できない)話に時間が取られることを、避けないといけません。
忙しい社長と話す時にダラダラ説明は出来ませんが、話の前置きが全くないと「前にも話した?そんなのいちいち覚えている訳ないだろう!分からないのに〇か✕かの判断が出来るか!」なんてオチにも繋がってしまいます。
話す側の注意点としては、伝える内容を「絞る」ことが何より大事です。膨大な情報を延々と話す人も多いですが、時間は有限であるのでそんなことをしてられません。でも、実際に世の中には「情報」を羅列して終わりの人が、本当に多いです。
大事なのは「ストーリー」をいかに伝えるかにあって、そのストーリーの精度によってその人の頭の良さがわかる様に感じています。適切な「比喩」や「対比」を用いて話す人は、その最たる例です。
会話の主人公を「相手」と考えてくれている人と、あくまで「自分」と考えている人は、社会人を続けていると本当によくわかります。後者の人とは、正直その後の関係性を築きたくはないですね…。
会社の業務で大きなものを線引きしていくと、必ず「会議」というテーマにあたります。先ほどの情報の「取捨選択」はもちろんですが、会議の目的は「何かの決定」になります。そこがズレてただの「情報共有会」にならない様に、会議のアテンド側に立った場合は注意をしたいところです。
本の中でも「因果関係を明確に」ですとか「目的から外れない」、「5W1Hを整理」といった記載は、本書でもあります。私も、賛成です。その中で少しアレンジを加えるとすれば、私は「自分なりの着地イメージを複数持つ」ということを気を付けています。
プランをA~Dくらいに想定しておき、その中でも優先順位をつけておきます。話の流れで最優先していたAではなく、Cになりそうなことは当然あり得ます。ただ「Cの中で②ではなく④に」の様なストーリーを描いておけば、現場で困ることはあまりありません。
「事前の想定外に出来るか?(多くは徒労におわるとしても)」という視点は、私の仕事の仕方としても、だいぶ確立されています。
最後に一般業務についても、少しだけ。本書で省みたこととしては「メールの長さ」でした。私は、とにかく文章が長くなりやすい(書きたいことが多すぎ)…。
「メールで背景なんて伝わらないよ」という一文に賛同し、これからはとにかく短くメールを書こうと心に誓いました。
また、立場上業務改善をすることも多いのですが、安易に「効率的」を重視するのは良くないという点にも賛同しました。「その制度が、どういう意味合いで出来たのか(あんまり意味ないことも多いけど)?」ですとか「その前後に、どういう関係者がいるのか?」といった視点が抜けていて、部分最適の業務改善になりがちなのが現実です。
「課題:こう変えたいという想い」と「問題:課題を変えるための障壁」をしっかりと区別して、広い視野で物事を判断しないといけないですね。
本書を読みながら「うんうん」と思う場面が、いくつもありました。自分一人であれば頭の中で勝手に組み上げているモノを、いかにアウトプットしなければいけないか。そしてそのアウトプットが、いかに相手に伝わっていない(かもしれない)かを、考えさせられました。
でも、こういった本に興味があると言うことは、やっぱり「自分一人」での仕事に限界を感じていたんだと思います。特に病気になって、誰かに無理やりにでも任せなければいけない場面を経験しているので。
「人に伝える」ことを、もう少し勉強していきたいですね。
本書、よろしければぜひ。
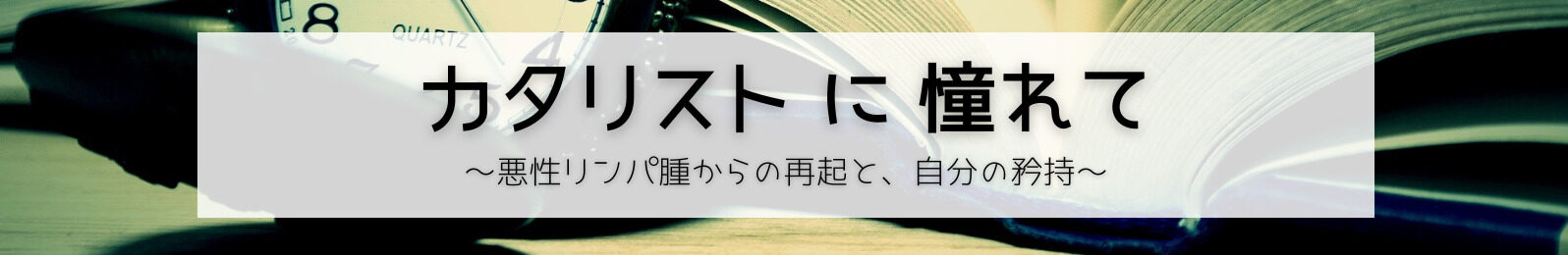

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45330b1f.368f98cd.45330b20.29ea5a4e/?me_id=1278256&item_id=19587668&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F4454%2F2000009064454.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)


